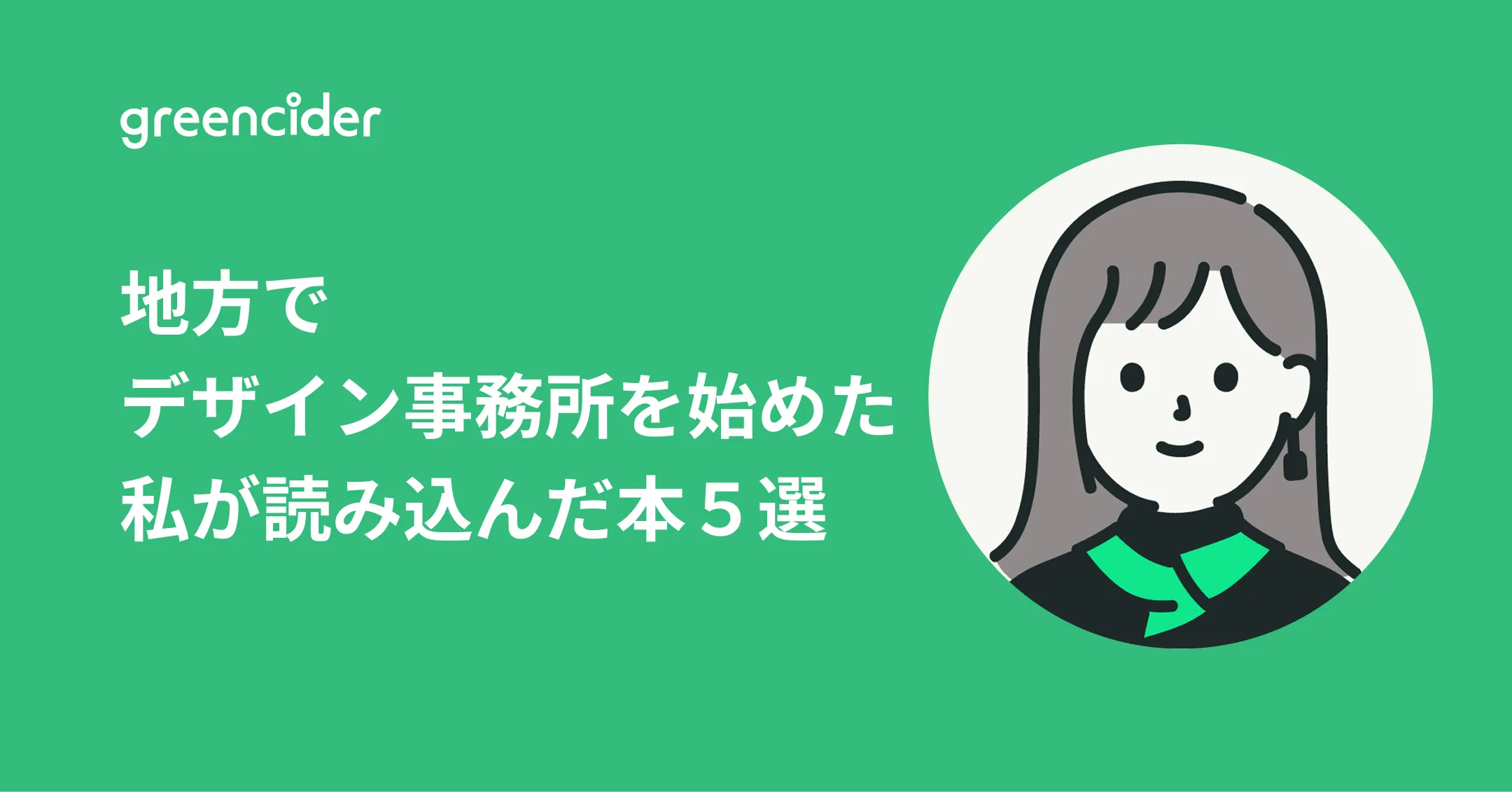
こんにちは、greenciderの古市です。
greenciderは、地元・三豊市をはじめ全国から10名以上のクリエイティブスタッフが参画し、クリエイティブを通して地域活性化や課題解決に取り組んでいます。このたび、スタッフの日常や興味関心、制作の裏側をお届けする「スタッフブログ」をスタートします!それぞれのスタッフの個性や学びを知ってもらうきっかけにしていただけたら嬉しいです。
第1回目は、ディレクターの私・古市が、地方でデザイン事務所を立ち上げるにあたって読み込んだ本を5冊ご紹介します。
地域×デザイン×コミュニケーションを学ぶ
「地方でデザインの仕事をするって、どういうことだろう?」
私は、新卒から大阪や神戸の制作会社で制作ディレクションやデザインを学ばせていただきました。香川県にUターンするにあたり、その経験が強固な土台になっていることは間違いありませんが、並行して地方特有の状況や課題を理解する必要も感じました。
今回はそんな中で、自分の軸をつくってくれた5冊をご紹介します。どれも単なるノウハウではなく、「視点の持ち方」「地域での仕事の意味」を深めてくれる本ばかりです。
1. 『地域の課題を解決するクリエイティブディレクション術』
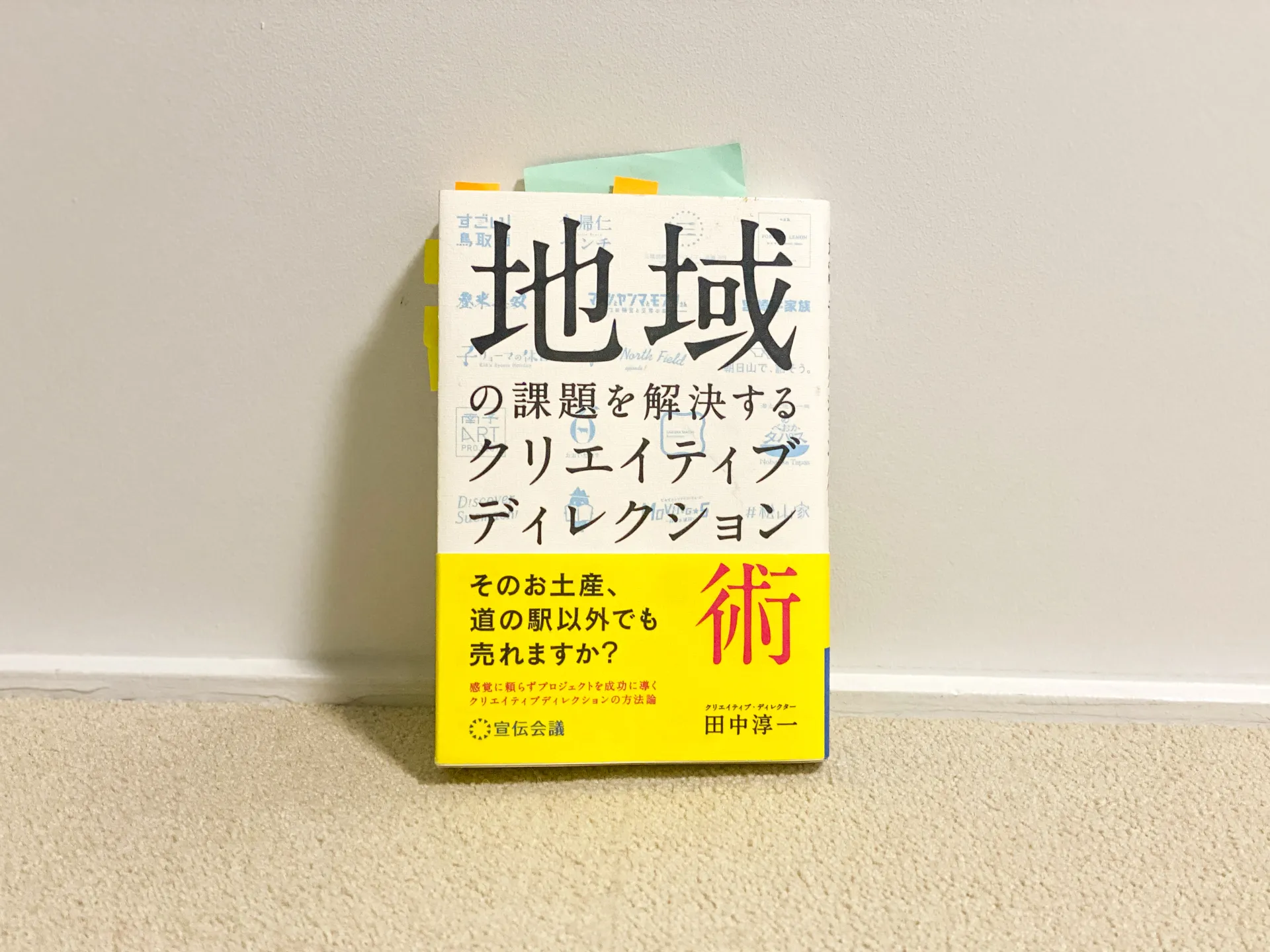
田中 淳一 著/株式会社宣伝会議
「地域にはクリエイティブ格差がある。地域に知見のあるクリエイティブディレクターが増える未来はもっと明るい!」
私の考え方や仕事の進め方の基礎となり、事務所立ち上げの背中を押してくれた本です。「クリエイティブディレクター」という職種は地方ではほぼ知られていませんが、デザイン・WEB・広告などを手がける上で欠かせないポジションです。地方でクリエイティブ仕事をする際の「リサーチ」「コンセプトメイク」「提案」や、厳しい予算で品質を落とさないための工夫、全国各地の事例などを通して、地方で本当に価値のあるものづくりを実現し、クリエイティブの価値を高める重要性を教えてくれました。greenciderが「何のための/誰のための仕事かわからない」「理由は無いけどなんとなく●●にしよう!」といった仕事のやり方を絶対にせず、お客様とのお話や企画といった“デザイン以外のプロセス”にこそ時間をかけているのは、クリエイティブディレクションを地域で実践しようとしているためです。
『地域の課題を解決するクリエイティブディレクション術』をAmazonで見る2. 『持続可能な地域のつくり方―未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン』
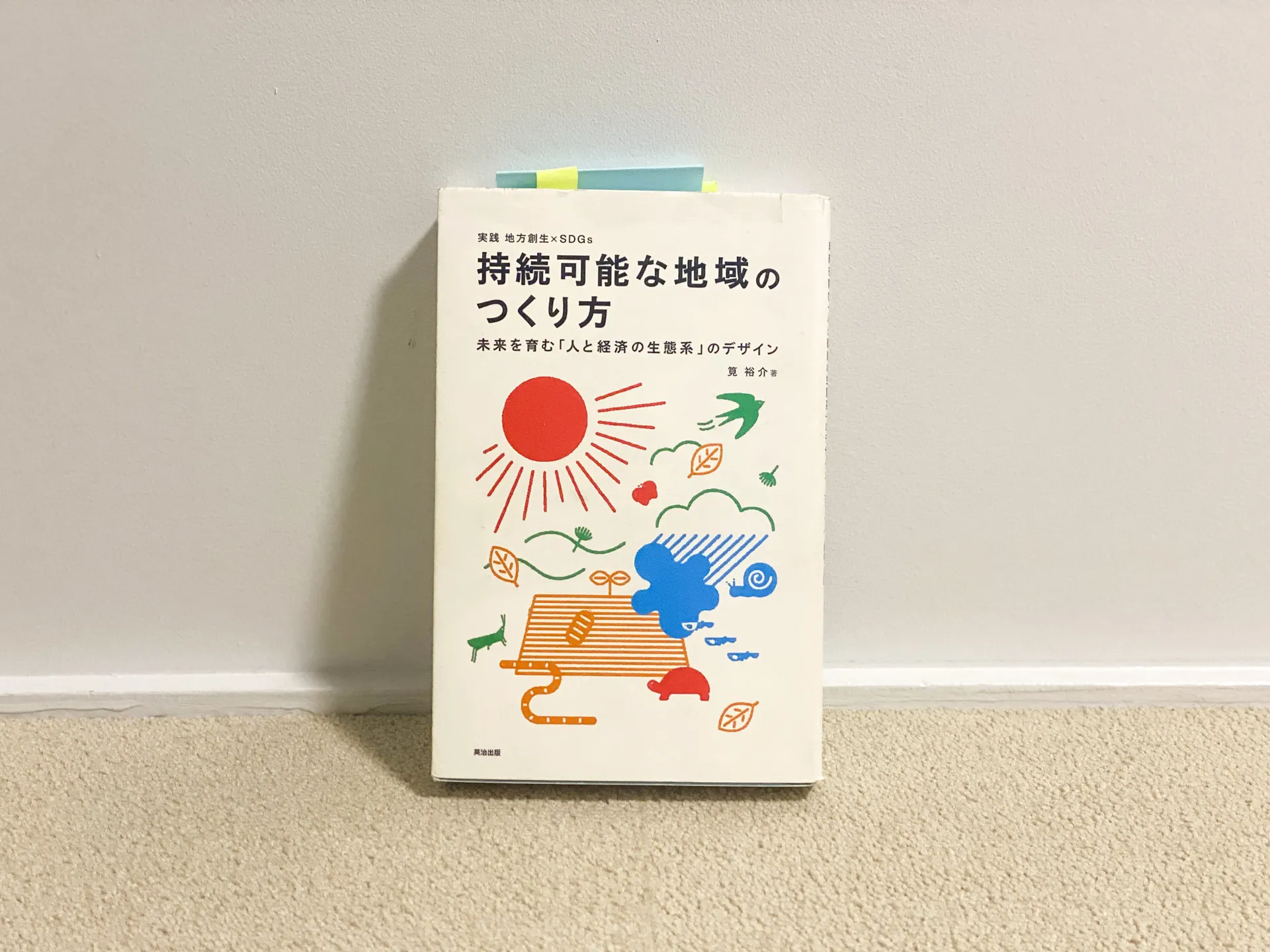
筧 裕介 著/英治出版
「土(コミュニティ)、陽(ビジョン)、風(チャレンジ)、水(教育)。地域の生態系をしなやかに再生する。」
私が地域課題とSDGsの基礎を学んだ本です。地域には人口減少から環境問題、農業、雇用、貧困、教育などさまざまな問題が絡み合って存在しています。この本は、それらの問題が相互にどう影響しているか、地域コミュニティでどう解決していくかを丁寧に解説しています。とくに本書後半で解説される「対話をつくる技術」「ビジョンの描き方」「問いの立て方」「次世代教育」などの手法はかなり実践的です。行政やNPOなどでワークショップを企画する方なども、この本はとても参考になると思います。greenciderは平たくいうとデザイン事務所ですが、「地域を観察する」「チームとして伴走する」「持続可能なものづくり」という3つのポリシーを掲げ、デザインの枠を越えたプロジェクトにも数多く関わらせていただいています。この本で学んだことが存分に生かされています。
『持続可能な地域のつくり方―未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン』をAmazonで見る3. 『ブランドをデザインする!』
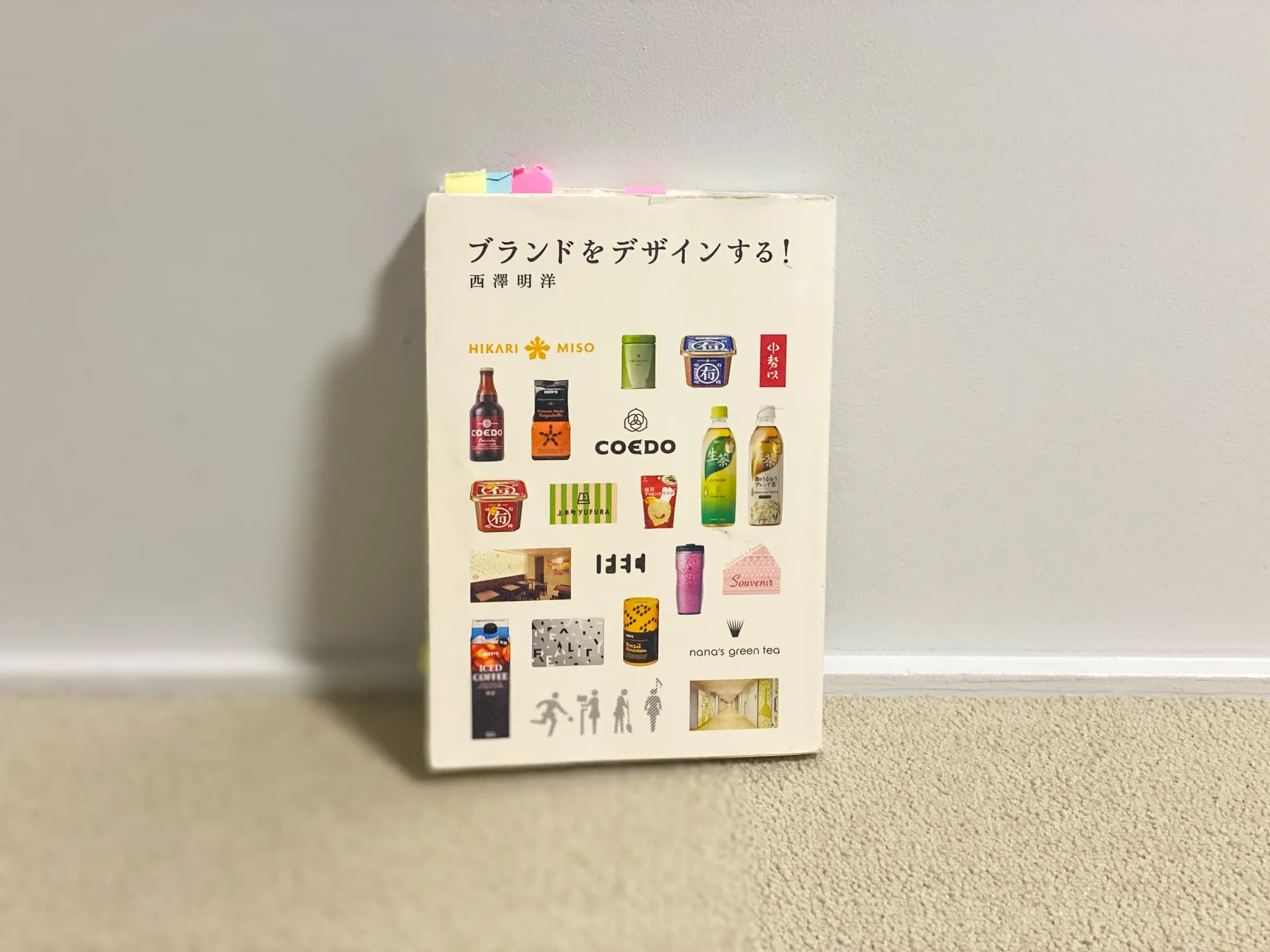
西澤 明洋 著/パイ インターナショナル
「ブランディングとは、ある商品、サービス、もしくは企業の全体としてのイメージに、ある一定の方向性をつくり出すことで、他者と差別化すること」
私の通っていた芸大の課題図書で、ブランディングデザインの基礎的な考え方を叩き込まれた本です。頭が働かない時にデザインを始めようとするとこの本が脳内に出てきて「今つくってもいいものはできないよ」と語りかけてきます。「デザインはセンスの仕事」と思われがちですが、実際は膨大なリサーチと泥臭い試行錯誤の積み重ねです。「綺麗な見た目を整える」ではないデザインの考え方、競合リサーチの方法、デザインコンセプトの作り方、ブランディングデザインを成立させる5つのポイントなど、デザインの本質を明快に解説しています。この本は地方にフォーカスしたものではありませんが、主題とする「ブランディングデザイン」は地方ではまだ十分に普及しておらず、今まさに求められている考え方だと思います。
『ブランドをデザインする!』をAmazonで見る4. 『ニューヨークのアートディレクターがいま、日本のビジネスリーダーに伝えたいこと 世界に通用するデザイン経営戦略』
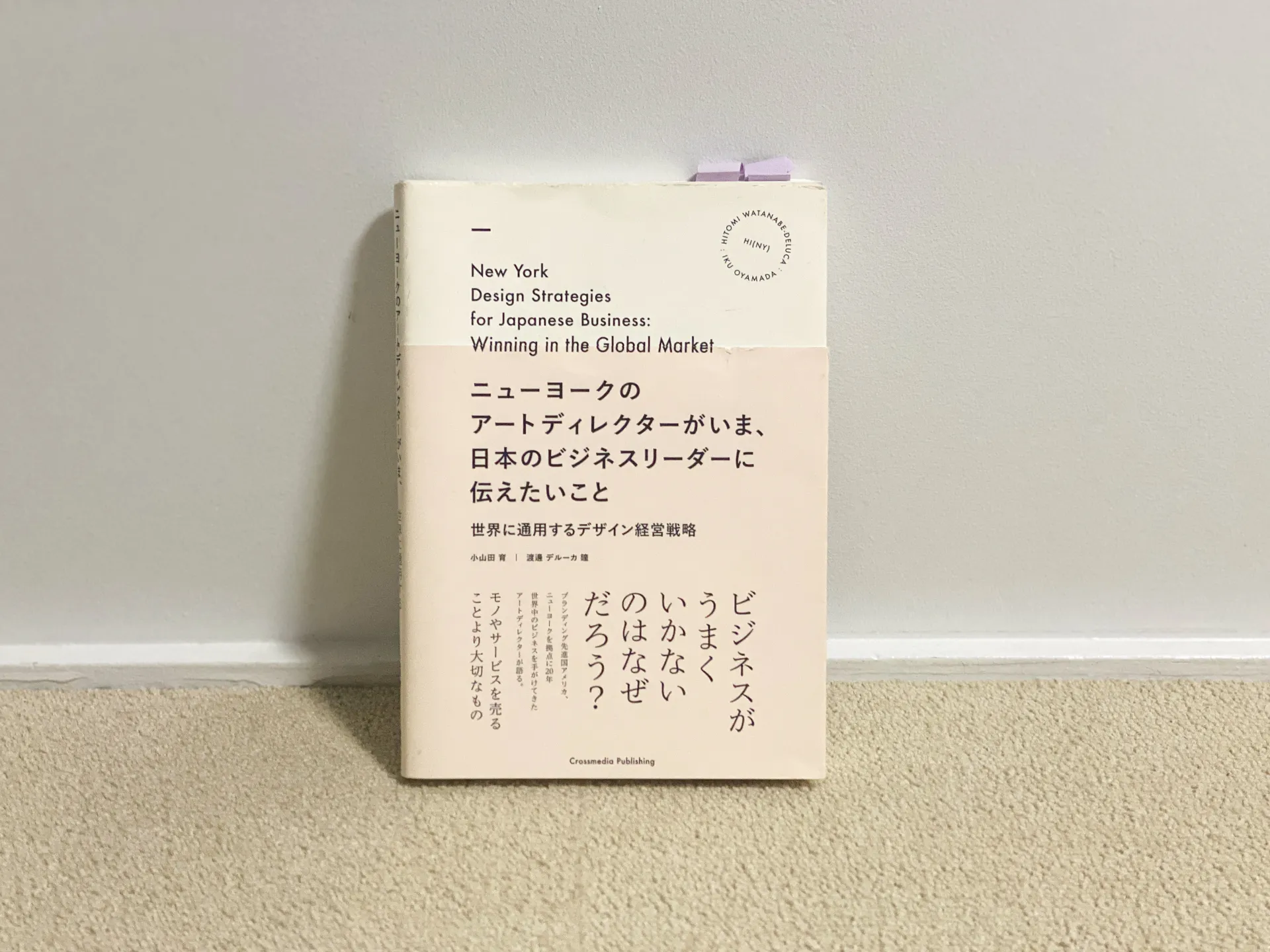
小山田 育, 渡邊デルーカ 瞳 著/クロスメディア・パブリッシング
「ブランディングの最終ゴールは、顧客ロイヤルティの獲得。すなわちファンになってもらうこと」
私がお客様の「らしさ」やつよみを見つけ出し、それをどう社会に伝えていくかを考える軸となっている本です。「世界と比較して日本は技術力や品質が高い一方、伝えることが不得意」という本書の言葉は、地方でも同じこと。農業などの第一次産業や製造業を担う地方企業へうかがうと、技術や意識の高さに驚かされると同時に、その良さを消費者にわかりやすく伝えるという点で苦労されているケースをよく目にします。その際は、本書に記載のある27のヒアリング項目を参考に、経営者や事業責任者の方に深くお話を聞き、社会に見つけられファンをつくるにはどこが鍵となるのか探るようにしています。特に近年重視されているという「SOCIAL: 社会貢献の要素がある」「ENVIRONMENTAL: 環境に優しい」「GOVERNANCE: 企業倫理・ガバナンスがある」「EMOTIONAL: 感情を引き出す」という視点を引き出しデザインに反映させることを、普段のプロジェクトでもよく意識しています。
『ニューヨークのアートディレクターがいま、日本のビジネスリーダーに伝えたいこと 世界に通用するデザイン経営戦略』をAmazonで見る5. 『問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション』
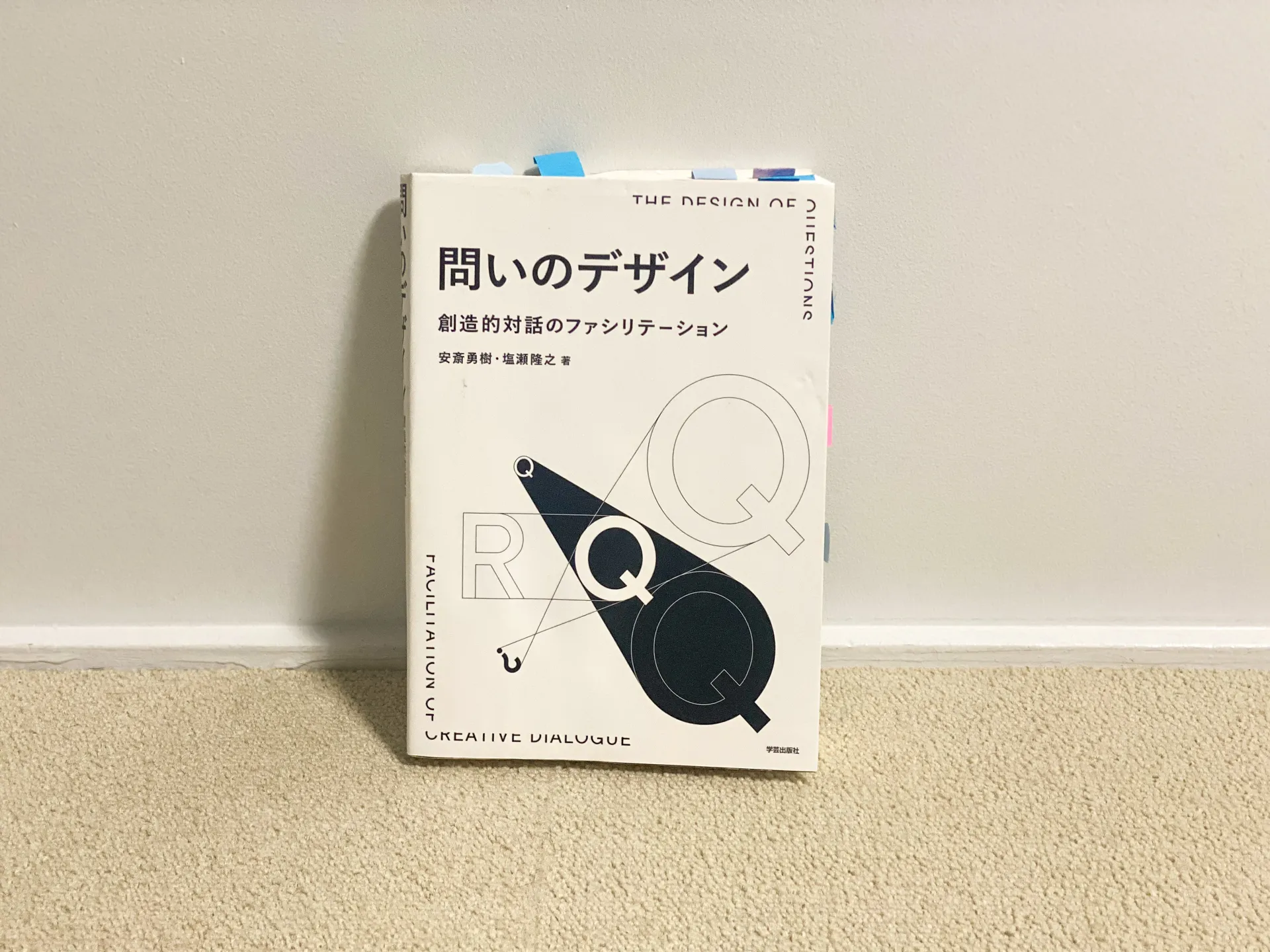
安斎 勇樹, 塩瀬 隆之 著/学芸出版社
「そもそも何を解決すべきなのか、『本当に解くべき課題』を正しく設定できなければ、根本的に解決の方向性がずれてしまい、関係者に『創造的な対話』は生まれない。」
私がワークショップ構築の教科書にしている本です。greenciderでは、企業のブランディングやロゴデザインを複数の従業員さんと一緒に取り組んだり、自治体とのプロジェクトで複数のステークホルダーとディスカッションする機会があります。ワークショップは、明確な設計なく始めてしまうと、次第に話が脱線したり重要でないことをいつまでも議論したりして、「結局なんだったっけ?」となってしまう危険があります。この本では、かなり具体的かつ専門的な内容で、参加者一人ひとりが創造的な意見を出せるようにワークショップを設計・運営する方法を解説しています。自分自身に問いを投げかけ、発想を広げるのにも使えると思います。
『問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション』をAmazonで見る以上、私が何年も手放せない良書5選をご紹介しました。greenciderの理念や仕事の進め方に、かなり影響を与えているものばかりです。興味を持った方はぜひ読んでみてください。
私たちgreenciderは「地域のクリエイティブ・パートナー」です。
スタッフそれぞれの専門スキルや興味関心を生かして、地域課題をクリエイティブの力で解決しています。
制作に関するご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、私たちgreenciderとともに、クリエイティブを通して地域課題や地方創生に取り組みたい方も、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせ|greencider(グリーンサイダー)
制作のご相談や見積もり依頼、その他お問い合わせはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
greencd.jp

