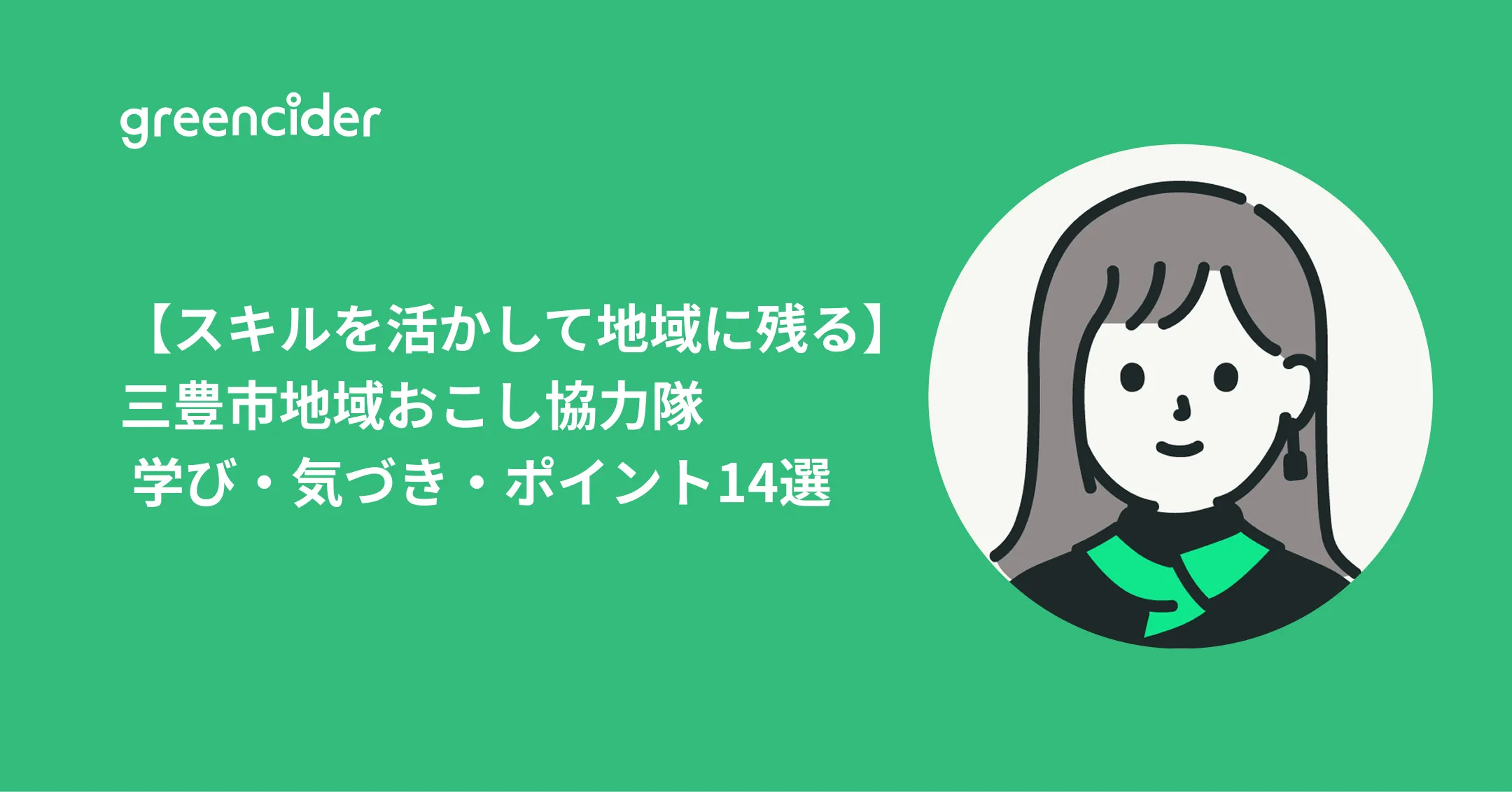
こんにちは、greenciderの古市です。
私は関西から地元・三豊市にUターンし、農林水産課地域おこし協力隊として活動を始めました。今年8月に3年間の任期を満了し、退任後もこの三豊市に残って事業を運営しています。これまでのキャリアを振り返ると、「地域おこし協力隊」という制度がなければ、地元に戻るという決断はなかったと思います。
今回は、地域おこし協力隊として活動した3年間で私が得た学び、気づき、そして活動の中で意識してきたことを、14のポイントにまとめてご紹介します。これから地域で活動したいと考えている方にとって、何かヒントになれば嬉しいです。
着任初期・活動組み立て段階
農林水産課へ着任した当初は、すぐに取り掛かる業務があるわけではなく、活動内容を自分で組み立てるところから始まりました。
- 農業の経験は全くなく、専門用語も知りませんでした。農産物の販路開拓やバイヤーとのやりとりも未経験でした
- 「販売促進」「担い手確保」「商品開発」など、幅広い課題の中から自分で何を進めるか決める必要がありました
- 地元出身ではありますが、10年近く離れていたため、家族や友人以外に人脈はありませんでした。ただ、土地勘があったのは大きな強みでした
そんな状況からスタートした私ですが、着任初期に特に大切だと感じたのが以下の5つです。
1. 月1の活動相談を所属課で実施
着任後すぐに、活動方針や困りごとを共有するための月1回の定例ミーティングを設けました。これにより、私は定期的にじっくり相談でき、職員の方も私が何をしているのか、何をしたいのかを把握しやすくなりました。
2. 自分の専門や得意が活かせそうな既存事業から
いきなり0→1を生み出すのではなく、すでに進行中の事業に参加することにしました。その結果、事業を通じて三豊のことや農業について学びながら、自分の専門性を生かしてさらに貢献することができました。
3. 市職員さんが地域中を連れ回し市民に紹介してくれた
着任してすぐ、市職員さんに地域のキーパーソンや若い農業者さんのもとへ連れて行っていただき、地域の方も温かく迎えてくださいました。私は「WEBやデザインができます」と自己紹介してまわることができました。
4. 市職員さんと地域の方々が「地域おこし協力隊」をよく理解していた
市の職員さんからは1年目から「古市さんのしたいことをしてくれるのが一番」「3年後のキャリアにどんどんつなげてくれたらいい」と常々言っていただきました。そのために必要なこと(人を紹介してもらったり、予算の相談に乗ってくださったり)も惜しみなく協力してくれました。また、地域の方々も温かく受け入れ、農業のことや地域の課題を教えてくれたり、人脈を広げてくれたりしました。このおかげで地域に馴染め、自分のスキルを活かすという方針で活動を組み立てることができました。
5. “できること”とセットで自己紹介する&してもらう
自己紹介では必ず「地元出身」「WEBやデザインができる」という得意領域を伝えるようにしました。市の職員さんも、私のことを同様に紹介してくれました。このおかげで、地域の方々にも覚えてもらいやすくなり、自然とデザインやWEBに関する相談をしてもらえるようになりました。
具体的な活動内容とその中で学んだこと
私の主な活動は、三豊市認定地域産品「みとよのみ」の広報プロモーションや販売促進です。「みとよのみ」は、生産者が開発した商品を市が認定し、プロモーションする既存事業ですが、広報業務などが一部停滞状態でした。私はウェブサイトやSNSの運用、生産者への取材・撮影、パンフレットのデザイン、マルシェへの出展などを担当しました。
6. 取材と情報発信は地域理解と人脈づくりに直結
生産者や販売店に取材し、記事をWEBとSNSで公開する活動を続けたことで、三豊を知り、人脈を広げることができました。1対1で話す機会が増え、「うちの商品を一番理解してくれているのは古市さんだから」と新しい仕事の相談をいただくこともありました。
7. 継続できること・継続できる場所を見つける
「みとよのみ」は私が立ち上げたプロジェクトではありませんが、自分にできるWEBやSNSから着手し、継続することで、バイヤーとの商談や新規認定品の開拓など、できることが増えていきました。また、月に1回高松のマルシェに出展し続けたことで、毎月楽しみにしてくださるお客さんもできました。大きなことをしなくても、何かを続けていれば価値になると感じました。
8. 0→1をつくるときは自分の得意を詰め込み、形に残るものにする
地域のニーズも大切ですが、「自分のためにもなるか」という視点を持つことも大切です。自分の得意を詰め込んだ有形の成果物を残すことで、退任後も活用してもらったり、困った時に思い出してもらえたらいいなと思っています。やりきるためには、自分の「得意・好き」が原動力になるなと思います。
9. スキルを頼られた時は必ず応える or 相談にのる
業務に直接関係がなくても、地域の方や他の部署の方からデザインやWEBの相談を受ければ、業務に支障のない範囲で必ず何かしら応えました。その結果、市のイベントのフライヤー制作など任されるお仕事の幅が広がり、実績が増え、それを見た方からまた新たな相談が来る、という流れが生まれました。
10. 協力隊活動と個人への依頼をきっぱり区別する
三豊市の地域おこし協力隊の制度上、特定個人や企業の利益となることはできません。「WEBサイトをつくりたい」「パッケージデザインをしてほしい」といった個人への依頼は有償・勤務日以外に対応しました。そうした個人へのご依頼が重なり、結果的に開業することになりました。
3年で得たものと任期満了後の進路
協力隊の3年間で、私は「人脈」「実績」「時間」という3つの大きな財産を得ました。
11. 地域内外のプレーヤー、自治体関係の方とのつながり
「地域おこし協力隊」という立場だからこそ、活動を通して半自動的に官民問わず幅広い方々と出会うことができ、口コミで仕事の相談につながりました。
12. 市関連の制作物やプロジェクトの実績
農林水産課の取り組みのみならず、他部署からのデザインやWEBに関する依頼にも応えました。結果的に計数十件の制作・プロジェクトに関わらせていただき、それがまた人脈づくり(口コミ)につながりました。
13. 固定収入を得ながら兼業で事業をつくる時間
三豊市の協力隊は基本週4勤務ですが、開業を機に週3日に変更してもらい、残りの時間で個人への依頼に対応しました。最低限の固定収入と保険があったので、任期終了後に向けた事業の体制づくりと両立することができました。これはフルタイムの会社員では難しかったと思います。
退任後、私は三豊市に残り、クリエイティブ事務所「greencider (グリーンサイダー)」を運営します。2024年4月に個人事業主として創業し、現在は「はじける地域をともにつくる」をスローガンに、全国から参画してくださっているメンバーの皆さんと運営しています。
14. 自身の事業でやりたいことをたまに口に出す・相談する
greenciderのお仕事では、営業活動をほぼ行っていません。「WEBの仕事したいな」「求人メディアつくりたいな」といったやりたいことをたまに口にすると、その後ご相談をいただくことになりました。信頼できる人には、自分のやりたいことを話してみるのも大切だと思いました。
最後に
関西で会社勤めをしていた頃は、地元に戻って起業するとは夢にも思っていませんでした。偶然見つけた協力隊の募集からご縁が始まり、3年後もこの地に残ることができたのは、三豊市職員の方々や地域の方々、関わってくださった皆様のおかげです。
もちろん、うまくいかなかったこともたくさんありますが、「地域おこし協力隊になってよかった」と心から思っています。周囲の方の理解と自分なりの工夫があれば、協力隊制度をうまく活用して地域に残ることができるという事例として、何かしら参考になりましたら幸いです。
私たちgreenciderは「地域のクリエイティブ・パートナー」です。
スタッフそれぞれの専門スキルや興味関心を生かして、地域課題をクリエイティブの力で解決しています。
制作に関するご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、私たちgreenciderとともに、クリエイティブを通して地域課題や地方創生に取り組みたい方も、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせ|greencider(グリーンサイダー)
制作のご相談や見積もり依頼、その他お問い合わせはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
greencd.jp

